
ヒゲオヤジ
プロローグ
2019年8月、ココナツ・クラブでの演奏のリズムツールとして、南米音楽フォルクローレで使われている太鼓-“ボンボ”があれば…と思い立ち、ネットを当たってみた所、3万円程度で入手できることは分かった。しかし、生来のモノづくり好きの性分から、「手作り」できそうじゃないか?という創作意欲が湧いてきた。
そこで、自作経験の紹介サイトはないものか…とネット検索してみたものの、破れた革の張替えの紹介サイトはいくつか見つけられたものの、残念ながら、ボンボをイチから手作りで作製したというものは見当たなかった。
視点を変えて、“太鼓作り” “drum making”というキーワードで検索してみた所、インターナショナルで様々な太鼓の製作過程が動画で紹介されており、それらを見るにつけて、何となく作れそうな気になってきた。中でも、日本の桶胴太鼓を自作したというサイトや、フレームドラムづくりの動画は、大いに参考となった。
実際に製作を開始したのは、思い立ってから2年後の2021年8月で、ちょうどコロナ禍スティホーム中のことであった。作り始めるまでの間は、ボンボの構造を調べて設計図もどきを書いてみたり、作業手順を考えたり、入手し難い山羊革を早めに入手したりと、準備期間であった。
参考にしたwebサイト
<ボンボ革張替え>
●ボンボ (南米太鼓) の リペアー
●ボンボの修理
●ボンボの皮 張り替え
●ボンボの皮 張替
<桶胴和太鼓づくり>
●自作桶胴太鼓にチャレンジ
<フレームドラムづくり>
●Bendir construction at the University of Athens
(Bendir (ベンディール)とは、北アフリカや南西アジアの木製フレームを使ったフレームドラムのこと)
※追記:一連の製作作業を終えて自作ボンボの完成をみた後、ネットサーフ中に、偶然、スペイン語版のボンボ製作サイトを発見した。疑問に思っていた点が分かる内容も含まれており、もっと早く見つけていれば苦労はなかったと思った次第です。
<スペイン語版ボンボ製作サイト>
●El arte de hacer un bombo
●BOMBOS- FABRICANTE ARTESANAL EN SANTIAGO DEL ESTERO
●COMO HACER UN BOMBO DE SICURI SEGUNDA PARTE
1. 製作構想
これまでボンボの演奏を見る機会はあったが、現物を間近で見たり触れたりしたことはなかった。
作成にあたって、web上の情報(写真・動画、太鼓づくり&リペア記事)を拠り所にして、手作りに向けた概略プランを練った。
基本構造や各部品の状態、作製の手がかりについては、十分、情報を得ることができたが、唯一、現物に触れてみないと分からない“革の張り加減”、“紐の締め加減”については知ることが出来なかった。
2. ボンボの構造確認
一般に、太鼓の基本構造は「胴」と「革(ヘッド)」からなり、「胴」に「革」を「キッチリ張る」ことで作られている。
洋ドラムでは、シェル(胴)にヘッド(膜)を当て、それ�をフープという丸い輪を用い固定しシェルに取り付けたラグと連結したチューニングボルトを締めることでヘッドを張る構造となっている。基本的に、ヘッドを強く張ると高い音が、ゆるめると低い音が出る。
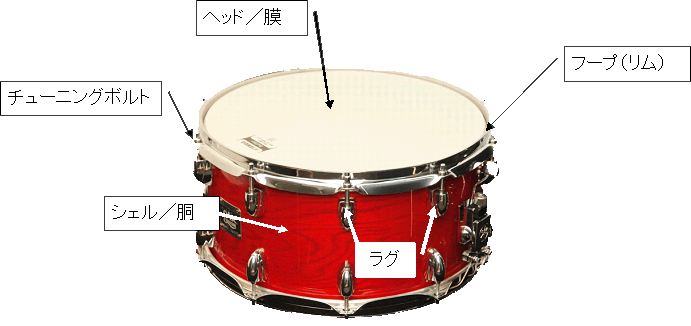
洋ドラムの各部の名称
和太鼓では、胴に革を緊着させながら、直接、太鼓鋲で打ち止めた長胴太鼓と、胴の両面からで金枠に張ったヘッドを紐で緊縛する桶胴太鼓(担ぎ太鼓とも呼ばれる)がある。

長胴太鼓(宮太鼓)
桶胴太鼓(担ぎ太鼓)
<ボンボの構造>
基本的には桶胴和太鼓とほぼ同じではあるが、ヘッドを締める方式が異なっている。桶胴和太鼓ではヘッドの縁に開けた穴に紐を通して胴に縛り付けていくが、ボンボでは、洋ドラムと同じよう、ヘッドをフープで固定して胴に緊着させる構造である。
ただしボンボでは、チューニングボルトの代わりに上下のフープを紐で締める方式となっており、この点は桶胴和太鼓と共通する。
ボンボに使われているヘッドは特徴的で、山羊革を毛のついたままで使っている。

ボンボ外観
.jpg)
ボンボ上面(ヘッド)

縛り紐を解いたところ

フープ(外枠)を外したところ

ヘッド(枠つき)を外したところ

ボンボの基本構造
3. 基本設計&材料準備
まず、作成するサイズの目安として、web販売品の仕様表記を参考に、太鼓胴の直径を38cm(胴回り 119.3cm)、高さ47cmとして進めることにした。
■太鼓胴用材
太鼓胴は、入手しやすさ、コスト、重量を勘案し、市販の桐材押し入れスノコを樽状につなげて作ることにした。
求めたスノコ板幅が5.2cm。これをつなげて胴回り約120cmの円筒にするためには23枚を目安とした。


スノコ板の木口面
購入した桐板押し入れスノコ
円筒形に成型するには、理想的には、板の接合端に8度の角度をつけたいところだが、その役を担う工具もないため、目分量のヤスリがけでお茶を濁すことにした。幸い、スノコ板の縦端がカマボコ状に丸みを帯びているため、成型するうえでの自由度は高かった。
23枚のスノコ板を円筒にまとめて接着するに当たり、板のズレを最小限にして、固定しやすいように、段ボールで簡易“サポート治具”を作ることにした。


サポート治具-段ボールで直径サイズの円盤を2枚作り、中心を支柱で連結させたもの
■ ヘッド用山羊革の確保
ボンボ自作の肝となる山羊革は、ペルーかボリビアから取り寄せなければならないかと思っていたが、インターネットのボンボ革リペア情報から、"ジャンベ"用の山羊革が入手できることが分かった。
アフロモード本店(https://www.afromode.jp/)サイトから一番大きいサイズ(縦横:87×74cm、対角線:98×100cm)をを購入した。
■ ヘッド用金輪の調達
革を張るヘッド用の金輪は、ホームセンターで見つけた「ポールプランタースタンド(7mm径の鉄材製)」から直径44cmの大輪を切り出し、太鼓胴のサイズに合わせて直径38cmに切り詰めた後、切断部を溶接して再接着し、輪に成型することにした。


入手した山羊革
ヘッドを張るための金輪用に入手したポールプランタースタンド
■ フープ(革締用外枠)の作製方法
フープ(革締用外枠)は、フレームドラム製作動画(Bendir construction at the University of Athens)を参考に、2.5mm厚ベニヤ板を3~4枚重ね、円筒形に成型して作製することにした。


丸めた薄板を重ねてボンドで張り合わせタッカーで固定し、固着後タッカー針を除去してヤスリがけ成型している
■ 張力調整用スライド・革サック
web画像で見ると、ボンボでは締め紐の張力調整のために革製のスライド・サックが用いられているらしい。
⇒これは廃カバンの革で手縫い作製することにした。
■ 締め紐
締め紐用として、クレモナ金剛打ち6号ロープをホームセンターで10m購入した。

締め紐の張力調整革サック
※冒頭でも述べたが、唯一の不明点はヘッドがどの程度の張力で貼られ、締め紐にはどの程度の張力がかけられているのか?ということで、現物を手にしたことがないので皆目検討がつかなかった。太鼓の鳴りはこれらの張力に左右されると思われるが、桶胴和太鼓では重要視されているが、ボンボの場合は、その構造や低音の響きが重視されていることから想像して、桶胴和太鼓ほど張力は高くないものと推察した。
4. 太鼓胴の作製
■ 胴の成型
<スノコ板の切断>
スノコを分解し24枚の桐板が取れた。これらを、作製するボンボの胴長47cmで切断し、接合面を40番のサンドペーパーでヤスリがけを行った。目指す角度は8度だったが、目分量でざっとかけるに留まった。

スノコを分解して板取り
<成型>
成型作業に混乱を生じさせないため、あらかじめスノコ板に、順番に、番�号をふっておいた
まず初めに、スノコ板2枚をサポート治具の外周に置き、接合面の密着度をチェック。甘い場合はヤスリがけ調整して密着させたうえ、接合面に木工ボンド塗布し、ずれないように治具の外周に両面テープで止め置きながら、順次、接合していった。
この作業は、胴回りをゴムバンドでタガ巻きしながら進め、全ての板を接合した時点で、接合面の微調整を行った後、ビニールロープで、緊く、胴回りを巻いて固定した。


ほぼ円形になっているので一安心

接合面の微調整後、ビニールロープで緊く巻いて固定
何とかつながった。作業途中の写真を撮る余裕はなかった
■補強とタガ締め
一晩置いた後、接合面をボンドで補強するとともに、胴内部に力木桟を止付けた

胴内部に補強のため、交差させた力木桟を二カ所に設置した。

胴内部の板接合面の隙間をパテで充填補強した。
胴表面と接合面のくぼみや隙間をパテで補修した後、やすりで丸みづけするとともに。胴外部からの補強として、直径3mmの針金を“二本ひねり”にして、胴の上下でタガ締めを行った。

タガ用に用いた3mmの針金“二本ひねり”
最後に胴の上下両端(唄口)の高さ不揃いをやすりがけで均等に揃えた。

胴の上下でタガ締めした
5. ヘッド用金輪づくり
ヘッドづくりの手始めに、革を張るための金輪づくりに取り掛かった。材料はホームセンターで見つけたプランタースタンド(鉄材の直径7mm)で、この上下についている大小ふたつの輪のうち、直径44cmの大輪をグラインダーで切離した。この大輪を完成した胴の外周に合わせ、少し余裕を持たせて(直径38cm+α)切断した後、切断部を電気溶接で再接合した。

プランタースタンドから大輪をグラインダーで切離


直径38cnnに縮めて切断した後、切断部を電気溶接で再接着した

心もとない溶接技術だったが、それでもしっかりと再接着することができた
6.外枠(フープ)づくり
● ベニア板切り出し
厚みのある円形の木枠を作るには、2.5mmの薄ベニアを熱成型し、数枚重ね合わせることにした。ベニア板を切り出すにあたり、長さは、直径38cmの胴の外枠となるので、計算上の円周は119.3cmとなるが、ゆとりを持たせて120cmを目安とすることにした。重ねる枚数は、必要な厚みに拠るが、金輪にしっかり圧力をかけて押さえるためには、金輪材の直径7mmより大きいことが条件となる。そこで、3枚で8mm、4枚で10.5mmを目安にして作成することにした。また、外枠の幅については、web画像から推測して6cmとした。
● ベニア板の丸み付け
薄ベニア板を熱湯に浸しながら、少しずつ丸めて、円形に成型し、完成した胴の外周に沿わせ、少し余裕を持たせながら合わせて切断した。
まず1枚目の板の両端を合わせて輪状にしておき、この接合部分をまたぐように、ボンドを塗った2枚目を外側から重ね、クランプで締め固定しながら、順次、タッカーで打ち止めて圧着した。

ベニア板を熱湯に浸しながら、少しずつ丸み付けを行う

タッカーで細かく打ち止めることで、1枚目と2枚目を圧着させる

1枚目の輪の外側に、ボンドを塗った2枚目を重ねて、クランプで止める

一晩おいて、固着を確認しながらタッカー針を除去
一晩おいて固着させた後、タッカー針をすべて除去し、2枚目と同様に、ボンドを塗った3枚目を、2枚目の接合部をまたぐように、外側から接着-タッカー固定した。さらに一晩おいて固着させた後、タッカー針をすべて除去した。
とりあえず3枚重ねで作製し、革張り・締め付け工程の段階でヘッド金輪との整合性を見ながら、外枠の厚みを調整することにした。(最終的には外枠内径が大きくヘッド金輪の固定に支障がでたので、半周分4枚目を内側に付け足した)

3枚目を重ね貼りして一晩おいた後の状態

タッカー針をすべて除去した後、サンドペーパーで成形

出来上がった外枠を胴にはめてみたところ、少し隙間のあくところが見られた(最終的には、この隙間を埋める形で半周分内側に1枚追加し、調整)。
7. 塗装
胴と外枠が完成した時点で、この両者に塗装をかけた。塗装前には凹み部分をバテで修正し、十分、ヤスリがけを行った。
外枠には、縛り紐を通すための穴を、1箇所2穴、7箇所に開け、紐の滑りを勘案して穴縁を整えた。
胴はチーク色、外枠はこげ茶色にした。

8. ヘッド作り(金輪への革張り)
<革張り手順>
● 革の切取りと下準備
革張りに備え、プランタースタンドから大輪を切離した段階で、革の上に縮める前の直径44cmの金輪を置いてみて、ギリギリ2枚取れることを確認しておいた。金輪をヘッド用に縮めて38cmにすると、折しろの余裕は3cmしか取れないことになるが、革は水に浸ければ伸びるので、縫い付け作業は何とかなるだろうと考えた。
革張り工程は、この時引いておいた直径44cmの輪郭線に合わせてカットして、一晩、水に浸しておくことから始まった。なお、金輪への縫込み作業効率を考えて、カットした革の縁には、あらかじめ、革止めテンション用の穴を、“菱打ち”を使って、円周上に対角線8方向で16ポイント開け、引っ張り用の輪ゴムをかけて置いた。
翌朝、革を水槽から取り出し、毛皮面をシャンプーとリンスで洗った。

革の上に切断・短縮前の金輪を置いてサイズを確認すると共に切取り用の輪郭線を引いておいた。

カットした革を、一晩、水に浸しておいた

直径44cmの輪郭線と縮めた直径38cmの金輪

翌朝、毛皮面をシャンプー&リンス
● フープにセット
革の端に開けた穴にテンション用輪ゴムをかけ、8方向から中心に向けて引き、革をフープに仮止めした。

水槽から出した革の上に金輪を置いたところ

輪ゴムを中心に向けて引き集め、革に適度のテンションをかけた状態で仮止めした
● 縫製
革のフープへの縫い付けは、菱打ちを使って2cm弱の間隔で穴を開けながら、ステッチャーで縫うという手順で行った。当初は、縫い目幅の目安となるガイド板を使うつもりであったが、実際に作業に入ってみると、手間取るばかりだったため、ほとんど目分量で縫い進めることになった。
1枚目に取り掛かっている間、2枚目は乾燥を防ぐため、濡れタオルで覆っておいた。

革の縫い付けは、まず菱打ちで穴を開け、そこにステッチャーの針を通して縫うという作業を繰り返した。写真の縫い目ガイドは、結局、使い物にならなかった。

完成したヘッド(表裏)。朝から始めた作業は、昼食を挟んで午後3時すぎまでかかったが、満足のゆく出来栄えであった。
9. 組み立て
<張力調整用スライド・革サックの作製>
組み立てに先立ち、フープを介してヘッドを胴に締めつける紐の緊張を調節するサックを自作した。
材料には廃カバンの革を活用し、ネット画像を参考に型紙を複数試作し、最適と思われるものを選んで型取りし、手縫いで7個作製した。


縫いあがった革サック7個
使用した革(カバン廃材)と型紙
<出来上がった各パーツの組み立て>
ボンボの作製も最終段階の組み立て作業となった。この作業は、胴の上下に濡らしておいたヘッドを宛てがい、ヘッドの金輪に外枠がしっかり当たるようにセットした上で、上下のフープ(外枠)に開けた穴と革サックに締め紐を通しながら、ヘッドを均等に締めていくという工程である。締め紐には、用意していたクレモナ金剛打ち6号ロープを使用した。
手順としては、底に下フープとヘッドを置き、その上に胴を立て、胴上にヘッドと上フープを被せ、上下のフープとヘッドがズレないようにしながら、一連の締め紐で全周均等に締め付けていくわけだが、これが思った以上に大変で、中々うまくいかなかった。特に、下フープの穴に紐を通すのに底を持ち上げる必要があるため、その際にヘッドとフープにズレが生じやすかった。
そこで、ツーバイフォーの廃材をクロスに加工してスタビライザーを2つ作成し、一つは土台にして、その上に胴を立てるようにセットした。もう一つのスタビライザーは上フープに乗せ、その上に漬物石をおいて上下のフープ・ヘッド・胴に均等に重みが加わる状態にした。そうすることで、下フープの底から指を回して容易に穴に紐を通すことができ、また、均等な重みがかかっていることで、バランスよく紐を締め込むことができた。
上下のフープに“張り”を加えるための紐の締め付けの程度が、前にも繰り返し述べたように、現物に触れた経験がないため、最も不明な点であった。構造の似ている桶胴和太鼓では、かなりきつく締め付けるようではあるが、ボンボでは低音の響きが出したいので、中等度の締め付けにすることにした。そして、一度にきつく行わず、時間をおいて革の乾燥状態、紐・フープの緩みや締め付けの偏りを確認しながら調整してゆき、革が完全に乾燥するまで、数日かけて慎重に行った。


下フープ穴に紐を通すのに十字型スタビライザーが役立つ

組み立て開始
上下にスタビライザーを置き、上のスタビライザーには漬物石を乗せて荷重した
革サックを通しながら、順次、上下フープの穴に紐を通してゆく

完成!
手探りで始めたボンボ作りも終盤を迎え、ついに、完成した。約2か月間にわたる作業であったが、大いに楽しむことが出来た。出来栄えはまずまずといったところだが、自己満足の域は出ていないかな(笑)。
完成したボンボを叩いてみると・・・・
完成後、早速、実際のコンサートで活用している。
第27回白神山地ビジターセンター「ふれあいデー」でのパプリカ演奏
第21回「うたごえ音楽会」での赤ちょうちん演奏